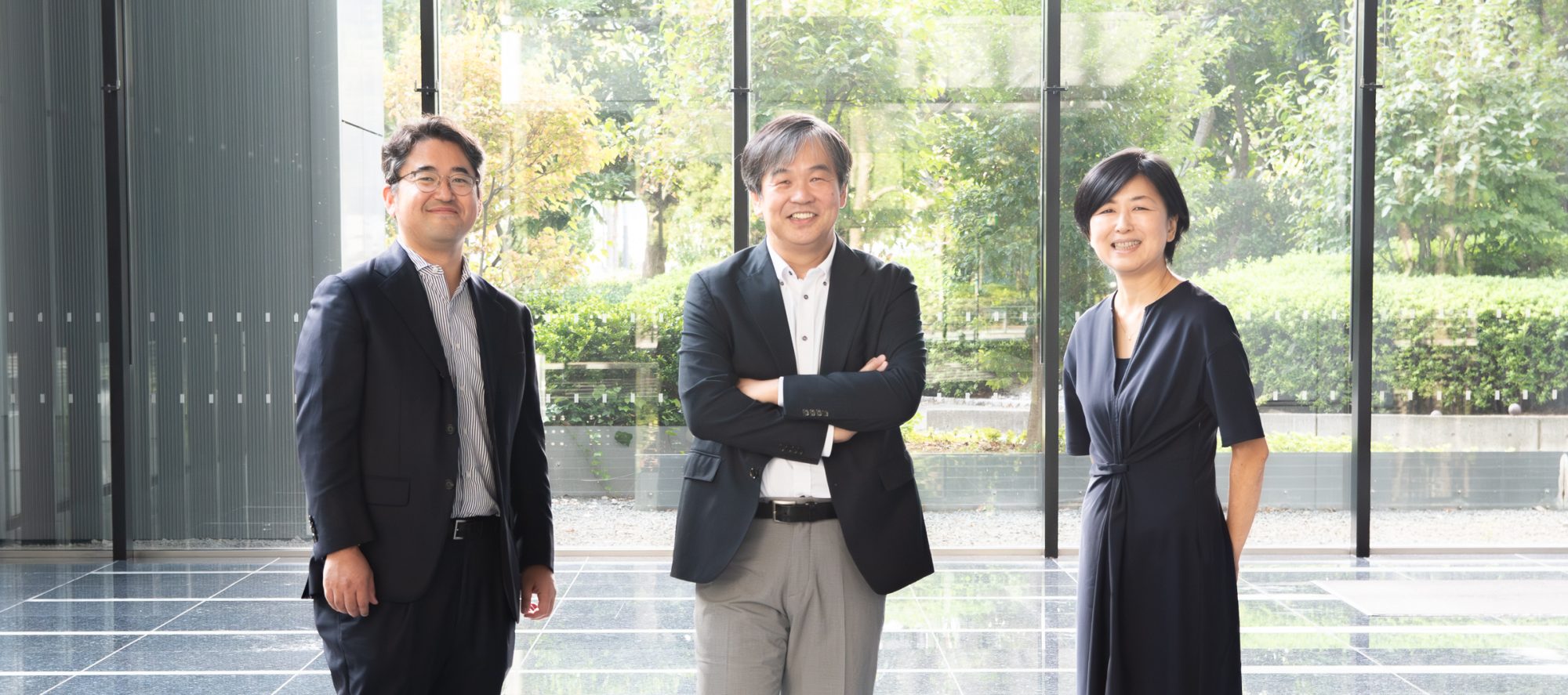政府が2020年12月に制定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、重点分野の一つとして水素と共に燃料アンモニアが明記されました。2022年6月、IHIグループは、ガスタービンで液体アンモニアのみを燃料にしたCO2フリー発電に世界で初めて成功。(プレスリリース)IHIグループがアンモニアに取り組むことになったきっかけをたどって、東北大学を訪れました。
2012年秋、ALCA(先端的低炭素化技術開発)においてアンモニアの燃焼に関するプロジェクトに参加した東北大学の小林秀昭教授。アンモニアは水素と同じく燃焼時にCO2を排出しない脱炭素燃料であると同時に水素キャリアであることから産業界からは注目されていたものの、「燃焼の研究者としては注目していませんでした」と言います。
実際、燃やしてもメタンと比べて発熱量は半分以下、燃焼速度も5分の1と遅く、安定した火炎を作るのが難しいため、燃料としてはほとんど使われていませんでした。窒素原子が含まれており、酸性雨の原因となり、排出規制がされているNOx(窒素酸化物)が燃焼時に発生する問題もあります。

「アンモニアを燃やすとむしろNOxがたくさん出てしまって手に負えないと、知識を持っているがゆえの先入観があったので、直接燃焼させるという発想は私のバックグラウンドからは出てこなかったですね」
しかし、燃焼性の低いアンモニアを燃料として使えるかどうか、燃焼速度や着火温度、最小着火エネルギーなどの特性、低NOx化に向けた方策などを調べるうちに、「技術的な開発リスクがとてつもなく高いものではないと認識でき、であれば面白いテーマかもしれない」と感触をつかみます。

小林教授には、また別の葛藤もありました。「東日本大震災で沿岸地域は人も住めなくなってしまい、あらゆる産業がなくなってしまいました。そんな中で当時、新しい脱炭素のロールモデルを作ろうというプロジェクトが次々に聞こえてきましたが、被災した人たちのケアとはかけ離れているように感じて、気持ちが乗りませんでした」と明かします。「それでも、原子力が当面使えない状況で、自分が関われる脱炭素プロジェクトとしてアンモニアが目の前に用意された。これはやっぱりやってみるべきだろうと」
翌2013年1月、小林教授は日本燃焼学会で復興支援を検討するために福島を訪れた際、同行していたIHIの藤森俊郎さんに相談を持ちかけます。現在、小林教授と同じ東北大学の流体科学研究所で特任教授を務める藤森さん。窓の外の雪を見ながら、「とても寒い日で、今日のように雪が降っていましたね」と思い出し、「帰りのタクシーの中で話を聞いて、アンモニアってそもそも燃料なのかと正直思いました」と振り返ります。

それでも、水素と同等にCO2を排出しない燃料として可能性があるという説明を聞き、「やりますよ」と即答。「どうのこうのと考えるより、20年以上の長い付き合いのある小林先生に相談していただいたことがありがたく、貢献したいなと思いました」
藤森さんは、褐炭から肥料の原料ガスを製造する二塔式ガス化炉の実証実験をインドネシアで行った経験があり、現地のアンモニア肥料工場も見ていました。「そこで1日1500トン作って、国際的に流通している。それを知っていたのも大きかったですね」
空気中の窒素と水素を直接反応させてアンモニアを合成し、「空気からパンを作る」とも言われたハーバー・ボッシュ法は20世紀初頭に生まれ、100年以上の歴史でその技術はブラッシュアップされています。作られたアンモニアはケミカルタンカーに積まれて世界各地に運ばれ、肥料や化学産業に使われています。
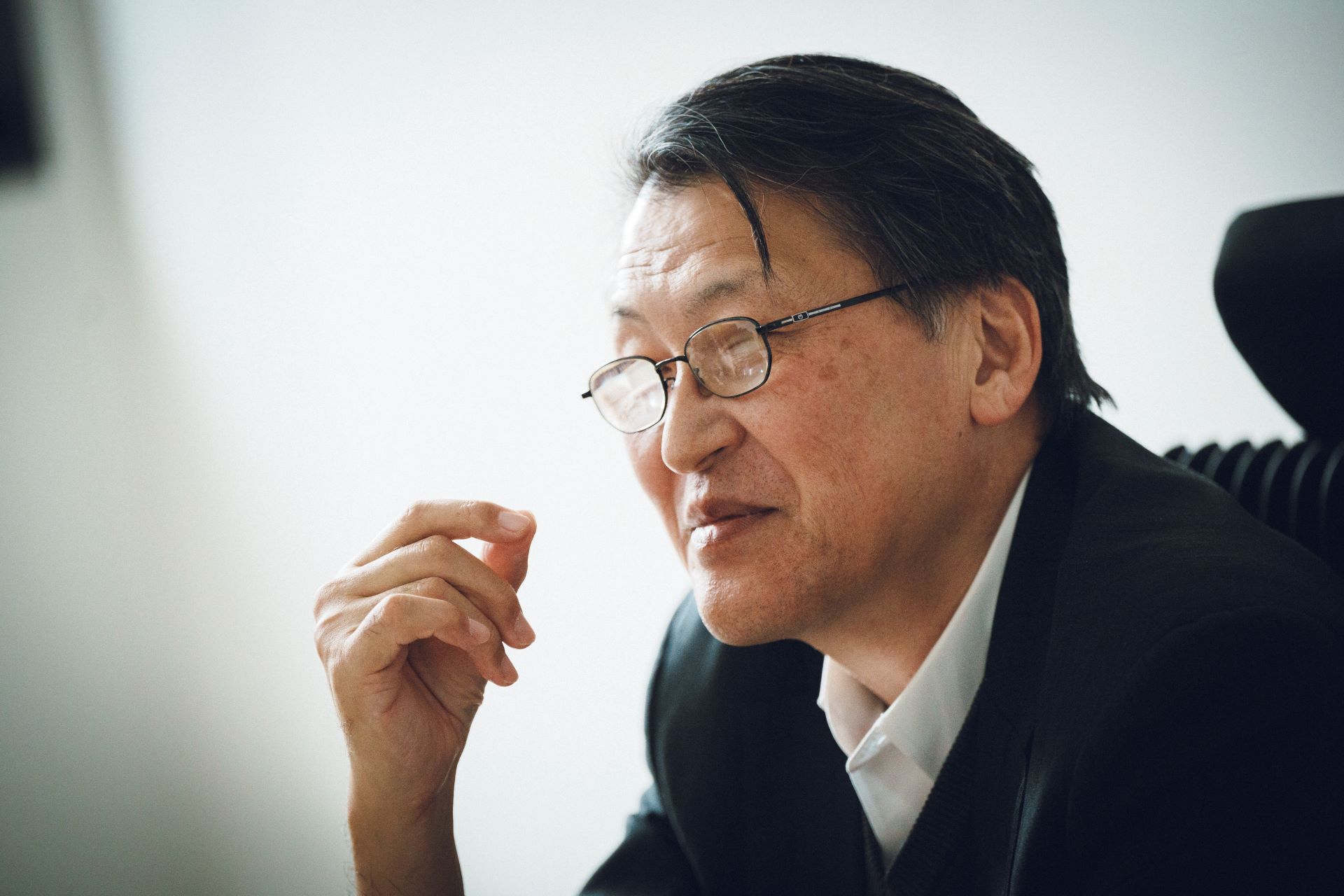
「周りは出来上がっているので、非常に有望だと思いました。水素キャリアとしてアンモニアから水素に戻すより、アンモニアを直接燃料として利用できれば、新たなコストを発生させずにより高効率で利用できる。残る課題は、どうやって燃やすか。それは自分たちの分野の技術的な課題で、技術者としての興味もあり、面白いじゃないかと」
その年にIHIの社内で小規模な研究プロジェクトを立ち上げ、アンモニアガスタービンの開発を始めます。「最初は自分たちで一度燃やしてみようという、本当に小さな試験からでした」と藤森さん。その後、ALCAを引き継いで2014年度から5年間にわたり実施された内閣府SIP「エネルギーキャリア」のプロジェクトに参加し、本格的な開発が始まります。最も重視したのは燃焼安定性でした。「ガスタービンは非常に燃焼負荷が高いので、不安定なものを燃やして、かつNOxも制御する装置を開発するというのは並大抵のことではない」と、熱量比でアンモニア転換率20%での燃焼を目標に、メタン100%から始めて徐々にアンモニアの割合を増やしていきました。
小林教授は「大学でしたら100%にトライして、できなくてもラボレベルの研究なのでいいんですが、多くの企業が参加しているプロジェクトでは、目標を定めたら実現する必要があるため、転換率20% は現実的な方向性だったと思います」と理解を示します。
燃焼器だけを取り出し、ガスタービンと同じ条件で行うリグテストでアンモニア20%の燃焼に成功。「燃焼技術的にはそれでかなりのことが分かるんですけど、それではインパクトがない」と、藤森さんは出力2000キロワットでの実証試験を提案。IHI横浜事業所に2000キロワット級ガスタービンを用意し、試験を始めます。

藤森さんは「実際のガスタービンは高速回転で出力しながら行うので、評価が全然違うんですよね。20%だったら成果も出るだろうという自信もありました」と振り返ります。
2018年4月、2000キロワット級ガスタービンでは世界初となるアンモニア転換率20%での燃焼に成功。(プレスリリース)ガスタービンの燃料としてアンモニアを利用する燃焼技術の実用化にめどを付けました。「これが大きい進展でした」と小林教授。藤森さんは「実際にやったのは現場の若い人たちです。非常に頑張ってくれて、なんとかプロジェクト期間内にちゃんと成果を上げるところまで持っていってくれました」とねぎらいます。
前述の通り、2022年6月には液体アンモニアのみを燃料にした100%専焼を実現。商用化に向け、長期耐久性確認試験を行っています。
並行して、石炭(微粉炭)火力発電におけるアンモニア燃料転換にも取り組みました。同じアンモニア転換率20%でも、ガスタービン等のLNG火力のCO2排出原単位は1キロワット時当たり約376グラムで、20%混焼時のCO2削減量は75グラムほど。一方で石炭火力のCO2排出原単位は1キロワット時当たり約864グラムなので、20%混焼時にCO2は173グラム近く減らすことができます。1
「ガスタービンは出来上がるまで足が長い計画になりますが、石炭であればもっと早くできて、エミッションのコントロールだけでNOxを下げられる。石炭ボイラの燃焼技術の開発や褐炭のガス化の開発も経験していたことが大きかったです」と藤森さん。電力会社にとっても石炭火力発電におけるCO2排出削減は喫緊の課題であることから、関心を持っていただけると見込んでいました。
2024年4月から6月までJERA碧南火力発電所(愛知県碧南市)の100万キロワット級大型商用石炭火力発電機でアンモニア混焼率20%での燃焼を3カ月間行い、従来燃料と比較してNOxは同等以下、SOx(硫黄酸化物)は約20%減少という結果を得ました。(お知らせ)現在、燃料転換率50%以上の燃焼技術の開発も進めています。
(本実証のストーリーはこちらから:脱炭素技術のトップランナーがタッグで挑んだ世界初のアンモニア燃焼試験)
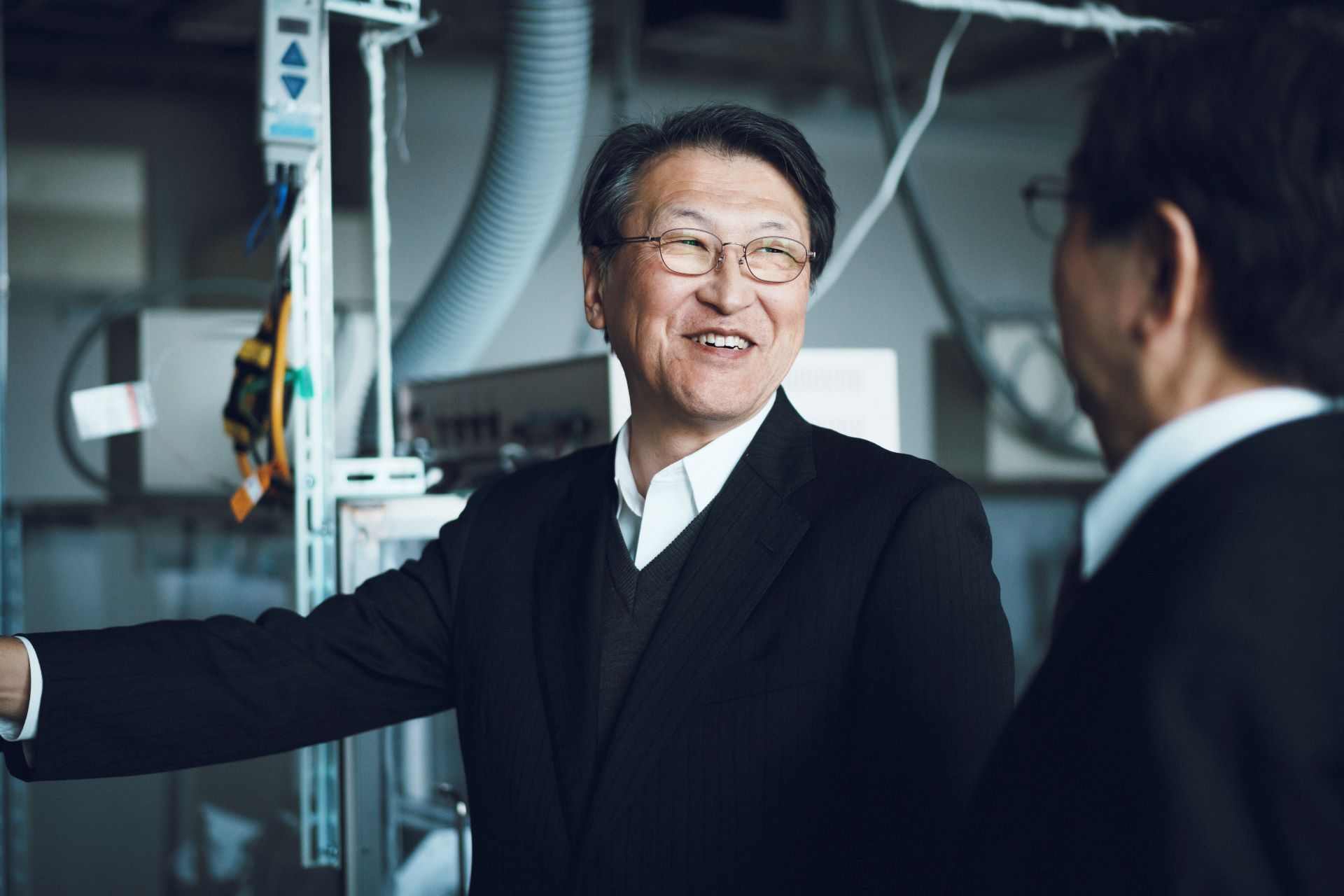
「相生でのガスタービンの耐久運転は25年度まで実施し、26年度にはマーケットに出すことにしています。GE Vernovaと行っている共同開発では今後、大型事業用のガスタービン向けに技術を展開します。(プレスリリース)それとは別にアンモニアの舶用エンジンについても、2024年9月から東京湾でタグボートによる運転試験を行っています。すでに商用ベースのものにアンモニアが搭載され始めています」と藤森さん。

そうした中で、小林教授は「これらの社会実装を確実に成功させることが大事です。それによりアンモニアに関する企業の認識が深まって、新しいプロジェクトも次々に立ち上がり、国からの支援も増えていくでしょう」と話します。
同時に社会の理解を深めていくことも重要で、「例えば環境へのインパクトに対する誤解がありますが、われわれはこの10年間で学んだことがありますので、丁寧に答えて対応していくことが必要です」とも。そして、「アンモニア利用に関する技術開発ができる技術者を増やしていくことも大切」と熱を込めます。
藤森さんは、アンモニア開発において日本に世界の注目が集まっていることを指摘。「一つはもちろん、アンモニアがこうやって使えるんだという利用技術。もう一つは、日本が大量にユーザーとなってくれそうだという点での注目ですね」。新たな需要を見込んで世界中のアンモニアのサプライヤーが興味を持ち、石油メジャーなど新たなプレーヤーも参加し始める動きがあるといいます。

「そういう意味では、次の大きなチャレンジがガスタービン。これが実現すると次世代燃料として普及する可能性が高くなり、実用化されればチェンジ・ザ・ワールドに近い大きなインパクトを世界に与えるはずです」
小林教授と同様、今後の技術者に向けても一言。「アンモニアは他の燃料とはかなり違う特性を持った燃料なので、われわれの燃焼技術はまだ入り口で、もっといろんな可能性がある。技術者の人たちはどんどんチャレンジしてほしい」と奮起を促します。
東日本大震災の影響で国内の原子力発電所が全て停止し、節電で照明を落とした暗い室内でアンモニアのエネルギー利用について語り合ったのが印象に残っているという小林教授と藤森さん。それから10年かけてアンモニア燃焼技術開発の「入り口」が開き、後に続く技術者たちに情熱は受け継がれ、開発は加速していくことでしょう。

取材協力:
小林 秀昭|東北大学流体科学研究所 教授
藤森 俊郎|東北大学流体科学研究所 特任教授 / IHI 資源・エネルギー・環境事業領域 技監
- 出典:日本における発電技術のライフサイクルCO2排出量総合評価
https://criepi.denken.or.jp/hokokusho/pb/reportDetail?reportNoUkCode=Y06 ↩︎